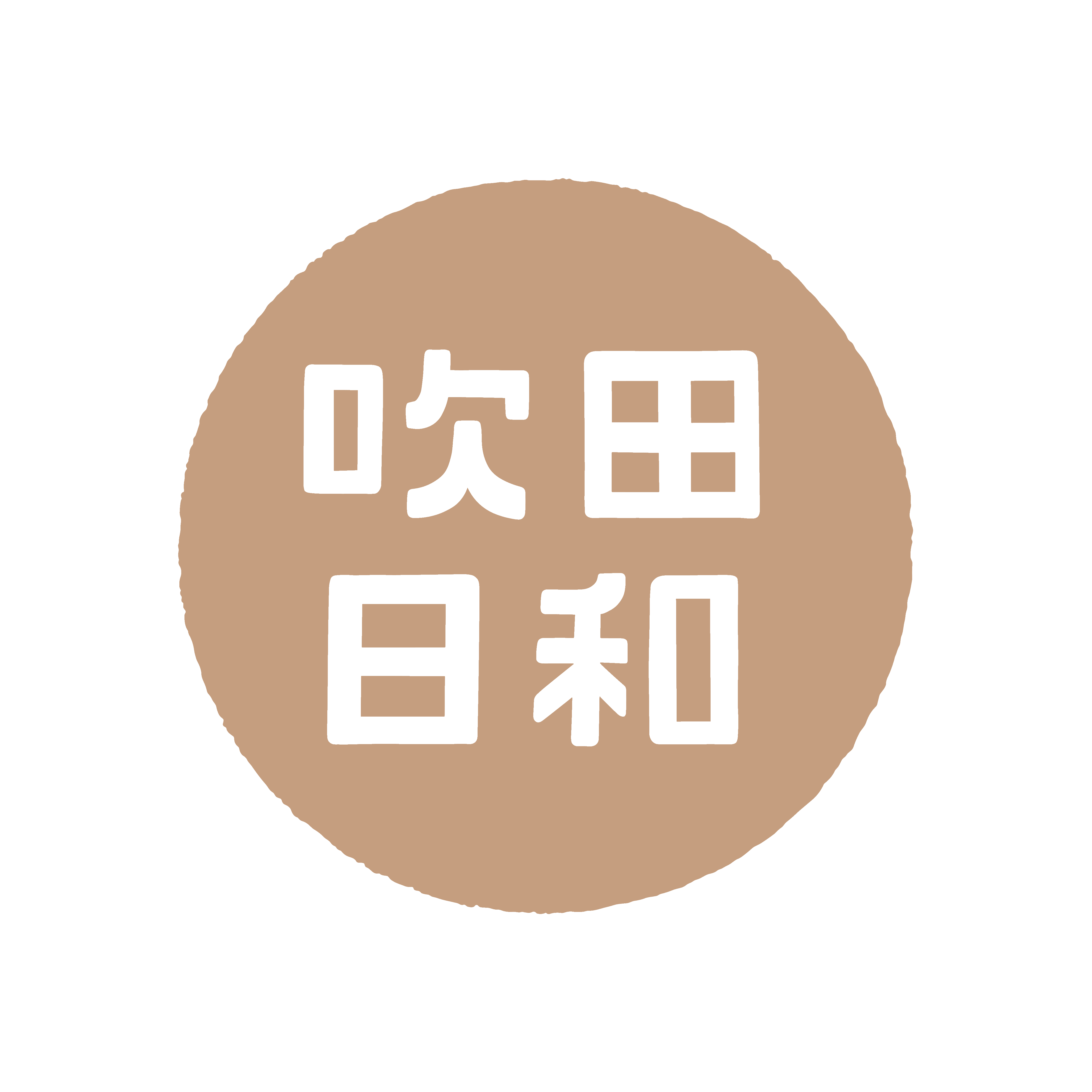吹田クロスで広がる未来 — 農業・自然・地域をクロスさせるアイデアと実践

日本の都市農業は現在、大きな転換期を迎えています。高齢化が進み、後継者不足の影響で宅地などに転用される農地が増えています。しかし同時に、農業を通じて得られる学びや喜びが、再注目される時代となっています。吹田市江坂にある平野ファームでの農業体験を中心に、農業、自然、地域がどのようにクロスし、未来に繋がる新しい可能性を生み出しているのか、吹田の農業に関わる3名が語り合いました。
登場するのは、平野ファームの平野紘一さん、株式会社midicaの西川聡さん、そしてパソナ農援隊・おおさかもんイノベーション代表の石井さん。彼らがどのように地域農業を支え、子どもたちとのつながりを深め、未来に向けてどんなアクションを考えているのかをお聞きしました。
対談者のご紹介

平野ファーム/平野 紘一さん
吹田市江坂にある「平野ファーム」を営む平野さんは、40年以上にわたり農業に携わってきたベテラン農家。地域の子どもたちに食育活動や農業体験を提供し、地元学校や保育園と連携して農業を通じた学びの場を作り上げています。

株式会社midica/西川 聡さん
都市部での自然体験イベントを企画運営する株式会社midica代表。都市農業の可能性を信じ、特に子ども向け農業体験に力を入れ、吹田市を中心に地域住民との交流を深めています。また、吹田市農業委員として、3期目7年目を迎えます。

吹田市在住/石井さん
吹田市生まれ、吹田市育ち。パソナ農援隊のメンバーであり、一般社団法人おおさかもんイノベーションの代表理事。農業と社会をつなぐ多くのプロジェクトを手掛け、後継者不足や空き農地活用に取り組んでいます。
「吹田市の農地、あと30年でゼロ?」――現状と課題

ー農地が1.3%まで激減。30年前は31%もあった?

大阪府北部に位置する吹田市。高度成長期の宅地開発や万博開催を経て、大規模な住宅街やオフィス街が立ち並ぶ一方で、まだ農地が残っていますよね。昔に比べると、やはり大幅に減ってきているのでしょうか?









そうなんです。実は僕、吹田市の農業委員をしているのですが、市のデータを見ると、60年前には吹田市全域の31%あった農地が、いま1%ほどしか残っていません。年々、宅地化や転用が進んでいて、このままだと30年後にはほぼ消滅するスピードで減っています。










全国的にも都市近郊農業は厳しい状況と聞きますが、この数字は確かに衝撃的ですね。









単に農地を「守ろう」と言っているだけでは解決は難しいですね。相続問題、さらには企業や自治体との連携まで視野に入れて取り組まないと、なかなか前に進まない。吹田市には企業や大学が多いので、うまく巻き込めば面白いモデルが作れそうですが、制度面の壁が大きいのが現実です。















私が農業を始めた頃は、吹田にはまだ農地が多かったんですが、千里ニュータウンや万博の開発によってどんどん農地が減っていってしまいました。もし農地がなくなると、子どもが自然に触れたり、地元で育てた旬の野菜を食べたりする場所が失われます。何とか守っていきたいですね。
ー「生産緑地制度」や税制の壁









特定生産緑地制度は農地を守るための仕組みですが、農家さんがなんらかの理由で営農できなくなったときに、後継者がいなくて農地を転用するケースも少なくありません。









そうなんです。行政が「税制や法律で農地を守ろう」と掲げても、どう守っていくのか、どう継承していくのかまではなかなかサポートしきれていません。。















私は実際に、周りの農地がどんどん減っていくのを見てきました。営農だけでは収益化は難しく、さらに年齢を重ねると作業が大変ですから。でも、本気で農地を守るなら、行政が企業や大学、そして市民を巻き込みながら地域のみなさんにとって有益な空間として、農地の多面的な機能を考える必要があると思います。
「子ども×農業」の力――そこで何が起こっているのか?
ー子どもが土に触れるとき、起きる化学反応












ここからは「子ども×農業」について伺いたいと思います。平野さんは長年、地域の保育園や小学校から子どもを受け入れていますね。どんな体験を提供しているのでしょう?















春に種をまいて、土の中で成長するのを見守って、夏や秋に収穫し、その場で食べる。葉っぱを触りながら「野菜ってこう生えてるんだ!」と驚く子もいます。親子で一緒に作業して、家族の絆が深まる場にもなっていると感じますよ。









僕が企画するイベントでも、収穫した野菜をそのまま焼いたり、調理して食べる体験が好評ですね。「野菜嫌いだった子が、自分で採った野菜なら食べられる」なんて声をよく聞きます。泥んこになって作業するのも、子どもたちにはすごく楽しいみたいです。実は、吹田市では、毎年市内の小学生約2,000人が「学童農園」を通して、農業体験をしています。
ー子どもの経験が「まちの原風景」を形づくる

















子どもの頃の体験って、大人になっても残るじゃないですか。かつて畑で遊んだ子が成長して、自分の子どもを連れてきてくれることもあるんです。そうやって農業を通じて世代間の思い出が繋がり、「まちの原風景」が醸成されるのは嬉しいですね。









子どもの頃に体感した泥の匂いや収穫の喜びは、大人になってからも忘れないものですよね。都市部であっても、少しの農地が残っているだけで、地域にとっては大きな価値があると思います。
後継者不足と空き農地――抜本的にどう変えていく?


ー後継者不足の根本要因「農業は儲からない?」










後継者不足は全国的な問題ですが、都市近郊の農業でも同じなのでしょうか?















都会にある農地だからこそ、特定生産緑地であれば税制面で優遇される一方で、農業をし続ける必要があります。農作業にやりがいを感じない方や、農地の存在意義をあまり感じない方にとっては、汗を流しても収入が安定しないわけですから、継ぎたがらないのもわかります。ただ、私は子どもたちの笑顔や地域の応援に支えられて続けてますので、そんなやりがいをみなさんに知ってほしいと思っています。









「農業=孤独で大変」というイメージを変えていく必要もあります。実際に人と交流が生まれ、農作業だけではない楽しみや社会的な意味もある仕事なんですよね。そこをビジネスモデルとして確立できれば、若い世代も入りやすくなるかもしれません。
ー「空き農地」が活用されない制度上の問題









市街化区域の都市農地は「農地」として守られている一方で、人に貸しにくいという課題があります。2018年に「円滑化法」という新たな制度が制定され、吹田市においては企業が貸農園として活用する事例も少なからずありますが、所有者とのマッチングがあまり進んでいないように感じます。。















都市農地は特定生産緑地制度の制限などで営利利用が難しかったりします。やりがいも見出せない、収益も少ない、借りたい人に貸せないとなると、結局、一部の農家だけが奮闘している状況になりつつありますね。
未来へ向けたアクションプラン―行政・企業・市民・農家がクロスする


ー行政・農家・市民・企業の連携モデル










では、今後どんな取り組みが可能でしょう? 行政や企業との連携について、ぜひお考えをお聞きしたいです。















農業と企業研修を組み合わせる形が広がってほしいと思っています。企業側はCSRや社員の健康増進にもつながるし、農家は人手不足を補える。そして、なによりも、地域交流の場にもなる。それを市が後押ししてくれると、さらに広がると思います。









「農業×イベント」の形も面白いです。地域のお祭りで農産物ブースを出したりされてますよね。そこに小学校や幼稚園の収穫体験を組み込んだり。さらに、企業からの支援を得られれば、地域の多様な層が呼び込めると思います。















それは私もやりたいですね。うちの畑は、すでに地域の子どもや大学生、企業の人が週末にボランティアや手伝いに来ることがあります。もっと大きなイベントとして広げるなら、コーディネーター役が必要。そういう役割を西川さんのような人が担ってくれると助かります。
ー平野ファームで開催された行政・農家・市民・企業の連携モデルの事例


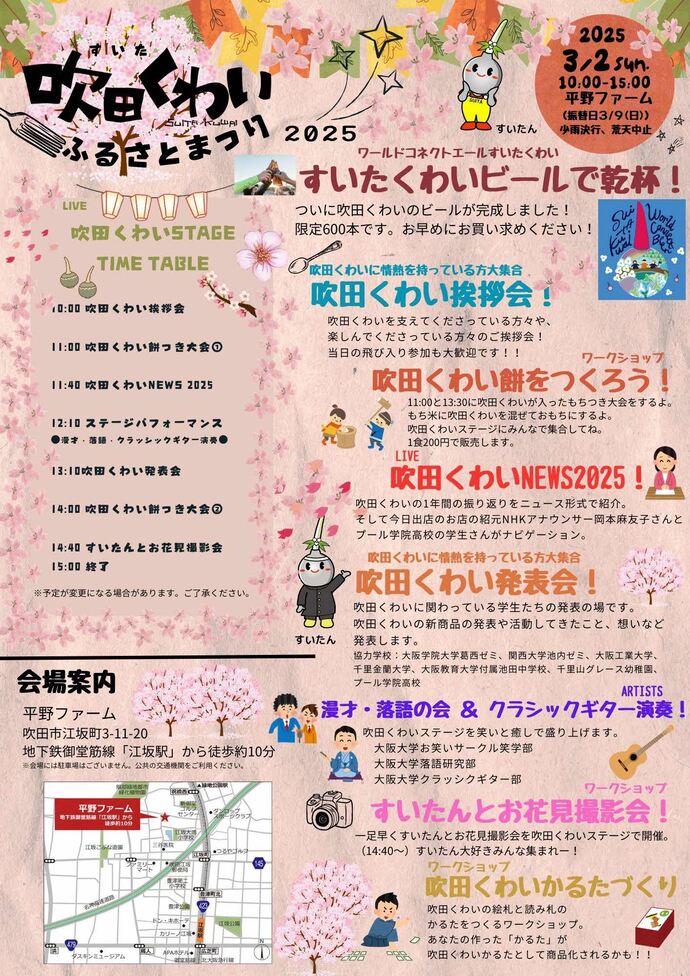
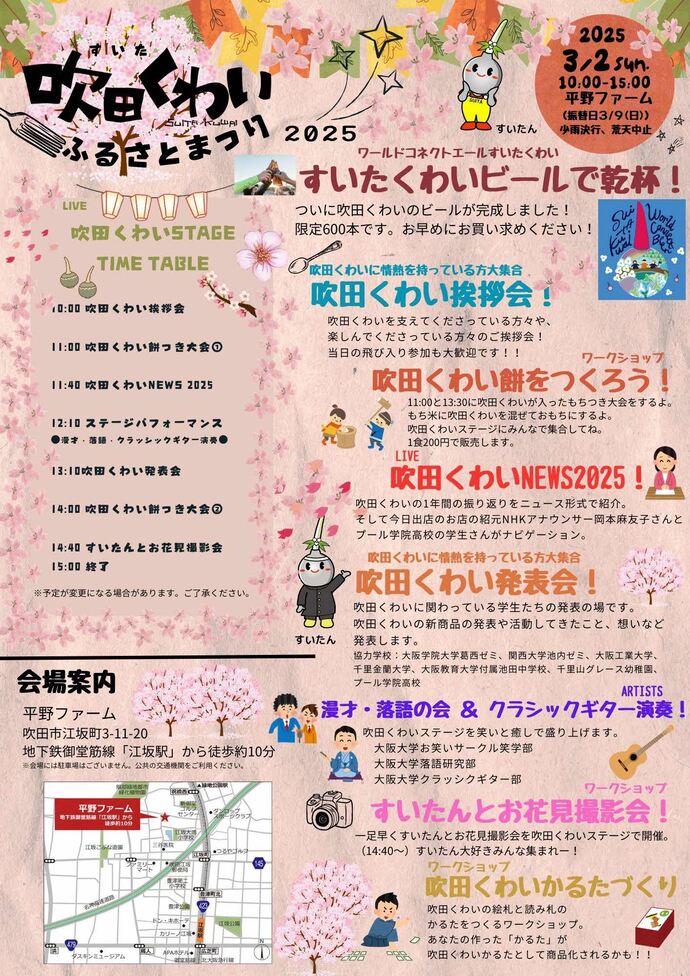






ー「農業×企業研修」や「自社農園」――制度の壁を超えられるか









週末に農作業を行う“二拠点生活”や、自社農園を作る企業の取り組みも各地で出てきましたが、都市部では制度的に難しいケースが多いですね。そこを行政と民間が一緒にサポートできれば、一気に広がるように思います。















行政が「吹田市の農地を守る」と今よりもっと大きな声で宣言してくれたら嬉しいですね。海外の都市近郊農業は行政が手厚く支えている例も少なくありません。吹田市でもそういう動きが出てくると、私たち農家にとってはとても心強いです。
「子ども×農業」が都市を変える――広がる吹田クロス
ー子どもが入り口、そこから地域コミュニティへ









子どもをきっかけに農業へ興味を持つ親御さんや企業、大学も増えています。最初は子どものためだったのが、いつの間にか大人もファンになる。そうやって広がっていけば、地域ぐるみで農地を支える土壌ができますよね。















私の畑にも、親子連れや学生が週末に手伝いに来てくれますが、すごく活気が出ます。野菜の育ち具合だけでなく、「最近どう?」なんて日常会話も増える。農業は“生産”だけじゃなく、人と人を繋ぐ役割も果たしていると実感します。
ー「一農家に負担が集中しない」仕掛けづくり










一方で、受け入れ準備や安全管理など、農業体験には負担も大きいのでは?















確かに、道具の用意やレクチャーに手間がかかります。一農家が全部を抱えるのは厳しいので、行政やNPO、大学生ボランティアとネットワークを組んで支援してもらえる仕組みが理想ですね。









体験企画を一度きりのイベントで終わらせず、継続的に関われるシステムを作れば、後継者不足の解消にも繋がるかもしれません。行政と民間が連携してプラットフォームを用意し、農家や参加者、企業とのマッチングを図るなど、コーディネーター役が必要ですね。
後継者不足の壁を超え、未来を切り拓くために


ーそもそもなぜ後継者は「農業を継がない」のか










後継者不足について改めて考えると、なぜ子どもや若者は農業を選ばないのでしょうか?















農作業の経験が少ないことや、「儲からない」「しんどい」「やりがいを感じない」ということだけでなく、相続時にあらゆる手続きが一気に負担になりますので、それが原因になっているのかもしれませんね。都会なら転用したほうが楽になれるかもしれません。。ただ、一度転用してしまうと、再び農地に戻すのはとても困難です。地域の子どもが土に触れて笑顔になっている瞬間を見るだけでも、やりがいは感じられるものです。そうやって、日頃から少しずつでも「やりがい」「地域にとっての重要性」を感じ取って、相続にはどんなことが必要なのかを早めに知ってほしいです。









ビジネス面とコミュニティ面を両立しなければ、後継者は増えにくいと思います。農業を多方面とクロスさせて、経済的にも将来性がある姿を見せることが重要ですね。
ー子ども・大人・農家が共に成長する社会へ









私が全国で見てきた中でも、子どもが農業体験をきっかけに親や地域を巻き込み、最終的に後継者が生まれるケースはあります。吹田は企業も大学も近いので、大きなムーブメントを起こせる可能性がありますよ。















私自身は85歳を超えていますが、できる限り農業を続けたいです。子どもや地域の人が喜んでくれるから。ただ、一人の力だけでは限界がある。市民、企業、行政が一体となって「農地をみんなで守る」流れができれば、30年後も農地を残せるかもしれません。
最後に――「農地を守り、未来を拓く」ためのメッセージ












最後に、視聴者や市民の方へ一言メッセージをお願いいたします。















農業は決して楽ではありませんが、子どもの笑顔や地域との交流が大きなモチベーションになります。近くに畑があるなら、ぜひ気軽に足を運んでみてください。土に触れ、野菜を収穫するだけでも自然とのつながりを感じられますよ。









「子ども×農業」の可能性は大きいです。週末や長期休みに少し体験してみるだけで、自然や食に対する見方が変わります。私たちもイベントを随時開催していますので、興味のある方はぜひ参加してみてください。









街に暮らす我々が農業について出来ることはもっとたくさんあると思います。例えばいつもじゃなくても、たまに推し農家さんの野菜を買って楽しむ、とか。
社団法人では農業に興味がある人と推し農家さんの農産物を届けるポップアップ屋台の活動をしたりしています。まずは楽しみながらできることからはじめていければと思っています。










今日はありがとうございました。子どもや若者が農業に触れる場がもっと増えれば、きっと吹田の未来は明るくなりますね。
吹田クロスで未来を描く


こうして3名が語る“子ども×農業”と“空き農地・後継問題”、そして“未来のアクションプラン”は、都市近郊である吹田市だからこそ生まれ得る多彩な可能性に満ちています。農業は生産手段にとどまらず、食育・地域づくり・観光・福祉・ビジネスと深く結びつく総合的なプラットフォームでもあるのです。
子どもたちの農業体験が空き農地の有効活用や後継者不足の打開へつながり、行政や企業、大学、NPOが一体となって地域コミュニティを再生する取り組みが、各地で少しずつ広がっています。
“吹田クロス”の名の通り、「○○×○○」の発想によって農業と地域が交わり、新たな価値を生み出す――。この対談が、より多くの市民・子どもたちにとって、農業や自然を“自分ごと”として捉えるきっかけになることを願ってやみません。
取材・文・写真:吹田日和